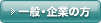�w������@1�@�\�@�\�w��(1960 �` 1977�N)[2017/03/22�X�V]

�@�u�\�w���v�́A�w���}������1960�N3���A���w��(�������L�����p�X)�ɗאڂ���Z�F�n�ɊJ�݂����B����܂ł͖��Ԃ̃A�p�[�g�Ȃǂ���グ�ė��ɂ��Ă���A�w�@�����O�Ō��݂����w���Ƃ��Ă͏��B�ؑ�������3���B�u�\�w�v�̖��́A�Z�c�E���]��s�Y���̕�̖��u�̂ԁv�ɂ��ȂށB�u���̕�̂悤�Ȕ��ɓ����̂���w�͉ƂŁA�������܂��₩�������w�l���A���̐��Ɉ�l�ł������ł���悤�ɂƐ[���S�Ɋ肤���̂ɁA���ɖ��t�����v�ƁA�Z�c����q�����Ă���(�u�S�����Âтāv)�B���ł́A���E�������āE����Ƃ��ďZ�ݍ��݁A�Ƒ�����݂ŗ����̎w���Ɨ��̉^�c�ɓ��������B���}�����◾�R�̑̈��(�ʐ^��1973�N�B�E�[�̃v���J�[�h�ɔ\�w�̎���������)�A�w�@���A�w����������Ă̗[�H��ȂǁA�y�����s�����Â��ꂽ�B���w�̐��_�Ɋ�Â��u���痾�v�̗��z���f���A�ƒ�I�łʂ����肠��w���̓`���́A�u�\�w���v�Ŋm�������B
�@
1960�N����2�N�ԁA�\�w���ʼn߂�������a�c��ߎq����(�Z����w���Ɛ��ȁ@1962�N��)�̘b�B
�u�Z���2�N�Ԃʼnh�{�m�̎��i�����E���Ƃ��Ƃ����̂ŁA�����̍��Z����i�w���܂����B�\�w���͐V�z�ł��ꂢ�ł������A�g�^�������ʼn��͓������ł����B
�@�ꕔ��6���4�A5�l������܂����B30�����炢�������ł��傤���B�Ǎۂɐl�����̕����ƍ��z�c����ׁA�z�c�͂т����艡���ɕ��ׂĐQ�܂����B��[�͂Ȃ��A�~�͉Δ��Œg�����܂����B�g�C���͋����A���C�͋߂��̑K���ցB�H���͊w�Z�̐H���ŐH�ׂ܂����B
�@���w�����͕��R������ȂNj����̋߂��l�Ɠ����ł����B�e���𗣂�ĐS�ׂ��Ƃ��ɁA���t���������������l�Ɖ߂����Ăق��Ƃ��܂����B���̌�͔��N�Ɉ�x�A�����ւ�������܂����B���Ȑl�Ɠ������Ă��䖝���邵���Ȃ��B�w�l����������x�Ƃ������Đ搶�̙z�Ƃ����������́A���ɂȂ��Ă��肪�����ł��ˁB
�@��6���ɓ_�āA���ꂩ��|���ł��B���X�����̐l�Ƒ��ɔ������ɍs���̂��y���݂ł������A����������ĂˁB�ĂȂ�܂����邢�����ɖ��߂��Ă��܂��̂ŁA���������ċA��܂����B��10���ɂ͏����ł��B�{��ǂނƂ��͘L���̓d���̉��œǂ݂܂����B�e���r���Ȃ��A���̐l�Ȃ�ƂĂ��߂����Ȃ����ł��傤���ǁA�����͂���Ȃ��̂Ǝv���Ă��܂����B�y���������ł���B�l���̈ꎞ�����Ƒ��̂悤�ɉ߂��������̒��Ԃ͐��U�̗F�ɂȂ�܂����B�����𗬂͑����Ă��܂��B��Γ����̘b�Ő���オ��A�d�b�͂������d�b�ł��v
(��)
�uMathTOUCH�v�Ő��������N���N���́\�\�ŐV���ʂ����ۉ�c�Ŕ��\��[2017/03/17�X�V]


�@������[�g�A�����ϕ��\�\�B�������p�\�R�����͂��悤�Ƃ��āA�͂��A�ƌ˘f���B�u2����1�v�Ɠ��͂��Ă��A�߂��������ɕϊ�����Ȃ��B�����c�[�������g���ɂ��A����Ȏw���L������͂�����A�e���v���[�g���琔����L����I��A�菇���ώG�ł킸��킵���B
�@����ȕs�����傭����̂��A�������̓C���^�[�t�F�[�X�uMathTOUCH�v���B������ǂݏグ��悤�ɑO���珇�ɓ��͂��A�X�y�[�X�������ƁA�ϊ���₪�\�������BX��2��Ȃ�AX2�B2����1�Ȃ�1/2�܂���2bunno1�Ɠ��́B�����A�����܂��ȓ��͂ł��A�����Ɍ�₪�����B�܂�ŁA���Ȋ����ϊ��̂悤�ɃX���[�Y�ŃX�g���X���Ȃ��B
�@�J�������̂́A�������w����f�B�A�w�Ȃ̕���N�v����(�ʐ^��)�BE���[�j���O�̃I�����C���e�X�g���ŁA�@�B�ɂ�鎩���̓_���s���ɂ̓f�W�^�����͂��K�{�����A���w�̉͑I�����⌊���߂��嗬�ŁA�v�l�͂𑪂�ɂ͕�����Ȃ��������Ă���B�����ŕ��䋳���́A�u�w�K�������l�����钆�ŁA�f�W�^�����̗�����������̂�����̂ɂ���ɂ́A����ł��g���鐔�����̓C���^�[�t�F�[�X���K�v�v�ƁA��6�N�O�A�uMathTOUCH�v���J�������B�]���̐������͕��@�́A�@�B���������t�H�[�}�b�g���邽�߂ɕK�v�����S�ȏ������[�U�[�����͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɑ��AMathTOUCH�͋@�B�̕����A���[�U�[�ɍ��킹�Ă����B�t�]�̔��z�����A�u�����͌���ƈ���ĕ��G�ȍ\�������Ă���̂ŁA�l�̎w���̂����܂��������e���āA�I�m�Ɍ����o���Ă���d�g�݂Â���͑�ςł����v�ƁA�U��Ԃ�B�w���ɂ����؎����ł́A�]�������Ɣ�r���AMathTOUCH���g�������������̓��͂ɂ����鎞�Ԃ���1.4�`1.6�{�����A����L�����o����K�v���Ȃ����Ƃ���A�����x�����������B���䎍����������Ɖ��ǂ𑱂��A�ŋ߂́AAI(�l�H�m�\)�̋Z�p�����p���邱�ƂŁA�����ЂƂ܂Ƃ܂�Ƃ��ė\������w�K�@�\����������B���܂�4000��̐������A85%�̐������ŗ\���\�B�s��ȂǕ��G�ȓ��͂���Ȃ��ł���B�O�p�������Ă��鎞���́A���̎�̐������D��I�ɏ�ʂɏo�Ă���̂ŁA�����͂��ǂ肻�����B
�@2015�N�ɓ����擾�B2017�N7���A�J�i�_�E�o���N�[�o�[�ŊJ�����uHCI(�q���[�}���R���s���[�^�[�C���^���N�V����)�v��c�Łu��ʐ����ɑ�����`������ϊ��̂��߂̗\���A���S���Y���v�Ƒ肵�A�ŐV�̐��ʂ\����B���łɉ����łȂ��A���쐬�ɂ����p�������uMathTOUCH�v�B2020�N�ɍT����f�W�^�����ȏ������Ɍ����A�܂��܂����ڂ��W�܂肻�����B
(��)
�w�����k�Z���^�[�̓R�~���j�P�[�V�����̗��K�̏�[2017/03/13�X�V]

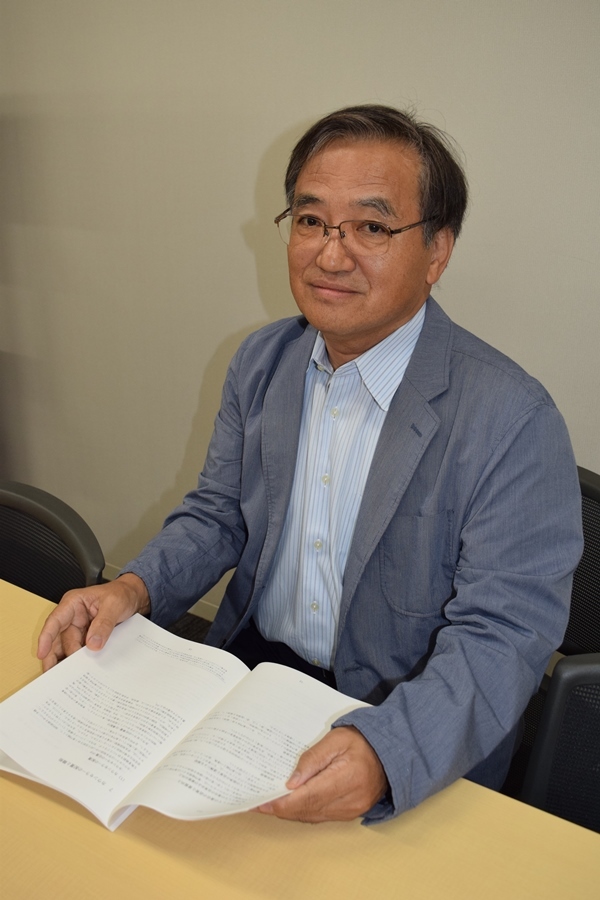
�@2017�N2���A���������̈ꎺ����Â��������Y���Ă����B�G�v�����𒅂����w���������A�s�U���n�ɔ`���R�ƃ}�V���}�����g�b�s���O�����`���R�s�U�Â���̐^���Œ�(�ʐ^�E)�B���Ő��n��L������A�A�[�����h���ӂ�����B�Ă��オ���҂�����Ȃ��l�q�Łu���������`�v�ƁA�I�[�u�����̂������B
�@�ꌩ�A���������̂悤�����A�w�����k�Z���^�[(��������)�̃O���[�v�v���O�����u���b(����)�₩�A���[�v�̈ꖋ���B����w�ɔ�ׁA�ފw�����Ⴂ�Ƃ����镐�ɐ쏗�q��w�Ŋw���x���̈ꗃ��S���A1965�N�̊J�݈ȗ��A�����I�ȏ�ɂ킽��A�S�̃Z�[�t�e�B�l�b�g�̖������ʂ����Ă����̂��h���������h���B
�@���炩�̔Y�݂�������l��O���[�v����̑��k���A�J�E���Z�����O���s���̂��傽��Ɩ����B1990�N�ɃZ���^�[�ƂȂ�A���k���e�̑��l���ƌ����̑����ɔ����A���݂͏T6���J�����A�w�����k����4�l�̐��őΉ��ɂ������Ă���B�p�����đ��k���K�v�ȃP�[�X�������A���k������2016�N�x�A���߂ĉ���2000�l�����B
�@�w���̂قƂ�ǂ��A�����I�ɗ������邪�A�u���̒��x�̔Y�݂ŗ��Ă����̂��ȁv�u�����Ƃ���ǂ��w�������Ă���̂ł́v�ƁA�~������������l�͑����B�����ŁA���������ł́A�ҍ��X�y�[�X�Ƀ\�t�@����ݕ��A�G����������A�������߂�����T�����ɂ��Ă���B�u�����̕ی����������S�n�������v�ƁA�v���Ă��炦����A���߂����̂��B���Z���^�[���ŗՏ��S���m�̖{���C�E���w������(�ʐ^��)�́u�w���ɋ��ꏊ���Ȃ��Ɗ�����w���A���Ă���w�������R�ɁA���S�ɋx�߂�ꏊ��������B�����ɗ���̂ɓ��ʂȗ��R�͂���܂���B�R�~���j�P�[�V�����̗��K�̏ꂾ�Ǝv���ċC�y�ɗ��p���Ăق����v�ƌĂт�����B�u���b�₩�A���[�v�́A����������g�߂Ɋ����Ă��炨���ƁA1994�N�x���猎1��y�[�X�ŊJ�ÁB�n���E�B���̃W���R�����^�����A�N���X�}�X�̃��[�X�Â���ȂǁA�G�߂��ƂɃe�[�}��ݒ肵�A������A���������ɑ����^�Ȃ��w���̎Q���������B
�@���E���Ƃ̘A�g���������Ȃ��B2009�N�x�ȍ~�A�e�w�ȁA�e�������ǂƂ̌𗬉���J�Â���ƂƂ��ɁA�u���E���̂��߂̊w���T�|�[�g�u�b�N�v��z�z���A����Ƃ̂Ȃ���𖧂ɂ��Ă���B
�@�J�E���Z�����O��A���C�Ɉ��A�ɗ���w��������A���̊Ԃɂ����Ȃ��Ȃ�w��������B���Ƃ���1�N�Ԃ̓t�H���[�ʐڂ��\�����A�ǂ����Ŏ�𗣂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�u�w������v�Ɍ��肳���h���������h�̋@�\���B
�@�{���Z���^�[���́u�X���[�Y�Ɋw�������𑗂�Ȃ��w���ɁA�O���C���̃`�����X��^����̂́A�Ō�̋���@��ł����w�̐ӔC�ł��B�w�����k�́A���l�̐��ݓI�Ȕ\�͂�L���A�������T�|�[�g���锭�B���i�I�ȑ��ʂ������B�L�`�̑�w����̈�Ƃ��āA�w�����k�Z���^�[�̉ʂ��������͂܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă��܂��v�Ƙb���Ă���B
(��)
�@
�R�g�o�̖��͂����\�\�\���ꕶ�������������ʊw���Ɍ��J�u���J��[2017/03/02�X�V]

�@���ʊw����2017�N2��18���A�����L�O�}���`���f�B�A�فE���f�B�A�z�[���ŊJ���ꂽ���ꕶ���������̌��J�u���́u�l�[�~���O�̃R�g�o�w�v��e�[�}�ɁA3�l�̌��������I���j�o�X�`���ōu�`������ӗ~�I�Ȏ��Ƃ������B
�@�\�\�O�������e�[�}�̐l�C�u���O�́A�^�C�g���Łu�����v���A�s�[������X��������B�V�F�C�N�X�s�A�́u�^�Ă̖�̖��v�́A�uMidsummer�v�̋G�ߊ��Ƃ��Ắu���āv�ł͂Ȃ��A�u���āv�B�ŋ߂̃L���L���l�[���́u�P�͈Ӗ���\���v�Ƃ����`���I�����̈ӎ��������A�����d�������X���ɂ���\�\�B���X�ɌJ��o�����l�[�~���O�́g�V���h�ɁA��ʎQ���҂�w����̓��������Ȃ��畷���������B
�@���ꕶ����������1988�N�ɊJ�݂���A�u�R�g�o�v�ɓ����������j�[�N�Ȍ����Œm����B2014�N�x�A�p�ꕶ���w�Ȃ̋ʈ��܋����������ɂȂ����̂��@�ɁA���{�ꂾ���łȂ��A������A�p��ȂǁA����̃t�B�[���h���L���Ă���B���J�u���́A�������ʂ�n��ɊҌ�����ƂƂ��ɁA�w���̒m�I�D��S�ɂ������悤�Ɗ�悵���B�����������Ƃ��J�u����̂͒������B�܂��A�ʈ䏊�����u�O�����w��i�̖|��^�C�g���̕t�����v�Ƒ肵�A�u�`�B�|��^�C�g�����u����v�u�J�^�J�i�u�������v�u�Ӗ�v�ȂǁA5��ނɕ��ނ��ďЉ��ƂƂ��ɁA���t�W���瑺��t���܂ŁA���{�̕��w��i�̃^�C�g�����A�p��łǂ��Љ��Ă��邩���l�@�����B�������̖|��Ɂu���Ⴖ��n�Ȃ炵�v��u�����u�v�Ȃǖ���^�C�g���������̂ɑ��A�ŋ߂͉p����J�^�J�i�\�L���������̃l�[�~���O���ڗ����Ƃ���A�u���{��ɒu��������w�͂�������A�Ղ��ɗ���Ă���̂ł́v�Ɩ���N�����B
�@�܂��A�ݖ{��H����́A�l�C�u���O�̃^�C�g������A�u���O�̃e�[�}�ɂ���āA������̎��Ȍ����~�������B�ꂷ��Ǝw�E�B�u�y�b�g���e�[�}�Ȃ玩���͍��q�ɓO���邪�A�O�����D���͎������O�ɏo��v�ƕ��͂����B�O�����̍��|�G�Y�������́A�l���̂����̕ϑJ�����ǂ�A�u�����̂��̂Ȃ̂ɁA�����Ō��߂��Ȃ��̂����O�B���Â��Ɍ������߂�C�������V���������̎g�����ݏo���A���ꂪ���s�ƂȂ��āA���O�Ɏ��㐫��t�^���Ă���v�Ɠǂ݉������B
�@�u���Ɉ��������A���̌������������ăV���|�W�E�����J�ÁB��ꂩ��u���Â��ɉ��炩�̃��[�����K�v�ł́v�u���O�͗e�Ղɕς����Ȃ����A�ǂ݂͕ς��Ă����̂��v�ȂǁA�����Ȉӌ����o�āA�u�l�[�~���O�v�ւ̊S�͐s���邱�Ƃ��Ȃ������B
(��)
���������ĔY��ł���\�\����͌���߂����AFD����J��[2017/02/24�X�V]

�@���N�E�X�|�[�c�Ȋw���̏��{�T�j�y�����̎��Ƃ́u�\�K���|�[�g�v�ɓ��F������B����̎��Ɣ͈͂����炩���ߋ��ȏ��Ŏw�肵�AA4�ꖇ�ɂ܂Ƃ߂Ď��Ƃ̏��߂ɒ�o����B�ӌ������߂�ہA�{�[�����g���̂����j�[�N���B�u���Ⴀ�A�{�[����������l�A�����Ă��������B�͂����v�B���{�y�������������{�[�����A���l�������A�܂��{�[�����n������ŁA�ʂ̐l��������B�������ăe���|�悭�A���^���J��Ԃ���邤���A��͉��܂�A���Ƃւ̈ӗ~�����܂�Ƃ����킯���B
�@�������A���̓��A�{�[����������̂͊w���ł͂Ȃ������������B2017�N2��16���ɊJ���ꂽFD(�t�@�J���e�B�E�f�x���b�v�����g=����͌���̑g�D�I���g��)����BFD�͑�w�ݒu��Ɋ�Â��A2008�N4���A��w�E�Z��ɑg�D�I�������`���t�����A���ɐ쏗�q��w�ł����N1������FD���i�ψ���𗧂��グ�āA���C����ƌ��J���Ɏ��g��ł���B���̓��͑�͌��ʊw�@���͂��߁A����I�ɏW�܂����������30�l���A�u�w�����w�Ԋ�т���������ƂƂ�?�`Teaching����learning�ւ̓]����}�邽�߂Ɂ`�v.�Ƃ����e�[�}�ŁA���{�y������̎�������ƂɈӌ��������s�����B
�@���ʋ��畔�̌Ö�v�y����������ɗ����A���ʋ���Ȗځu�{��҂ށv�Ŋ��p���Ă���u�L�҉�����v���Љ���B�w�����u�L�ҁv�ɂȂ��āA�Q�X�g�X�s�[�J�[�⋳���Ɏ��X����𓊂�������X�^�C�����B������̎�����A����������I�ɒm����������]���̍��w����A�w����̂́u�A�N�e�B�u�E���[�j���O�v�ɂǂ��]�����邩�ɏœ_������B�Q��������������́A�u�w���̎�̐��������o���ɂ́A��������Ă���A�Ɗ��������Ȃ��H�v���厖�v�u������߂Ă�����Ƃ��n�߂�ƁA�~���ɐi�ނ����łȂ��A�}�i�[���悭�Ȃ�v�ȂǁA�������鐺���オ�����B�������m����݂�����������̂�FD�̃����b�g���B���鋳���́u����グ��̂����v�Ƃ����ӌ������������ɁA�u�����ɂȂ肽�Ă̂���́A���������w����{����Ă����v�u�����c�ɂ�������Ă͂��߁v�u����������݊��ׂ��ƁA�w���ɋ�����ꂽ�v�ȂǁA�����Ȑ����������B
�@��̏I�ՁA�u�x�N�g���������Ɍ�����v�Ƃ����t���[�Y���A�����̋����̌��ɂ̂ڂ����B�x�N�g���͍��A�ǂ��������Ă���̂��A�w���̂����ɂ��Ă��Ȃ����A�����ɉ��P�̗]�n�͂Ȃ����\�\�B�������Y�݂Ȃ���w���Ɍ��������Ă���B�����Őԗ��X�Ȍ�荇���́A���ɐ쏗�q��w��FD�̃x�N�g�����ԈႢ�Ȃ��A�����Ɍ����Ă��邱�Ƃ������������B�@
(��)
�@