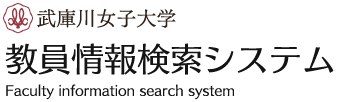教員情報詳細

- 所属名称
-
文学部 日本語日本文学科
- 資格
-
講師
- 学位
-
博士(言語文化学)
- 研究分野
-
応用言語学, 在外ベトナム人研究, 日本語教育学
- キーワード
-
自律学習, エスノグラフィー
- ホームページ
人生のあらゆる局面において、人は多かれ少なかれ何らかの移動を経験するのではないでしょうか。移動に伴う新たなことばとの出会いとその習得、そのことばを使用する際に感じる感情やアイデンティティの変容、そして、移動の経験を語ることば等に関心を持っています。
移民に対する現地語の教育としての「日本語教育」や、日本生まれの第二世代以降の移民の子どもにルーツの言語を教育する「継承語教育」といった領域と重なりますが、教育の現場に限定せず、フィールドワークや生活史の聞き取りを通して、生活の中にあることばの現実を捉えたいと考えています。
1978年から2005年まで日本はベトナム難民の定住受け入れを行いました。ベトナム難民が日本での生活を始める前に受講することができた日本語教育は3か月から4か月程度で、それ以降、日本語教育を受ける機会がないまま40年近く日本で生活されている方もいます。このような現実を踏まえ、先行研究ではベトナム難民の日本語能力が「欠如」していることやホスト社会側からの「支援」の必要性が訴えられてきました。
もちろん必要な支援体制を整えていくことが重要であることは言うまでもありません。しかし、日本語母語話者との比較から、かれらの言語能力が「欠如」していると捉えてしまうと、当事者の視点から見たことばをめぐる経験が捉えられなくなってしまうという危惧も生じます。
私はこれまでベトナム難民として来日された方にインタビュー調査を行ったことで、複数の言語とその他の能力を組み合わせながら、日本での生活を切り拓いてきたことを明らかにしてきました。調査協力者の語りを聞くことによって、日本語母語話者が「当たり前」と感じて気づかないことや、言語教育において「常識」とされていることが揺さぶられていく感覚を味わうことができるのです。
私自身の研究は、日本語教育への関心から始まりましたが、上述の通り、移住者の経験にも広く関心を持つようになりました。フィールドワークの過程で、ベトナム語メディアにも携わるようになり、私自身も「ベトナム」にまつわる経験をどのように語っていくのかが問われるようになってきました。
調査をしていると、現地語の習得に関する語りを聞くだけではなく、世代を越えて自分たちが使用してきた言語を継承してほしいと願う第一世代の声が聞かれることもあります。言語の継承はそれだけで進展するのではなく、その言語の使用される行為とともに引き継がれてこそ、生きた言語の継承につながると言えるのではないかと感じるようになりました。
ベトナム語で実施される宗教活動や、ベトナムに関連したアート活動などで参与観察を行うことで、ルーツや家族についての経験や記憶が言語とともにいかに継承されようとしているのかといった点についても関心を抱きながら調査を行っています。